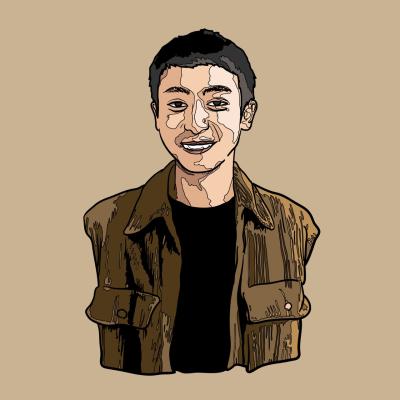メジャー帰りでもっとも強くなった投手
まずはこちらのデータをご覧いただきたい。五十嵐亮太の成績を3つの期間に分けたデータだ。
・1998-2009年 507登板/47勝/29敗/54S(セーブ)/53H(ホールド)/防御率3.45
※1998年は一軍登板なし
・2010-2012年 83登板/5勝/2敗/0S/4H/防御率6.41
・2013-2020年 316登板/18勝/10敗/16S/110H/防御率2.28
1998-2009年がヤクルトでの“メジャーリーグ挑戦前”の成績、2010-2012年がメッツ、ブルージェイズ、ヤンキース3球団という“メジャーリーグ”での成績、2013-2020年がソフトバンク、ヤクルトでの“メジャーリーグ挑戦後(日本球界復帰後)”の成績だ。
この成績を見るにつけ、五十嵐はメジャー帰りの投手で、NPBでも成功した選手の一人と言っても過言ではないだろう。アメリカで身につけた変化球、投球術、思考法……メジャーリーグでの経験を糧に、さらに強くなった――。変化することを恐れず、常により良いものを求め続けた五十嵐。プロ野球選手生活12~14年目という、一般的に言う“ベテラン期”に差し掛かった時期に身を置いたアメリカでの軌跡を振り返る。
アメリカでのカルチャーショック
2009年オフ、五十嵐はFA権を行使してアメリカへと渡った。最大の武器である最速158kmのストレートと、フォークボールだけを携えて。当時、それまでに12年間を過ごしていたヤクルトでは、クローザー・林昌勇へとつなぐ不動のセットアッパーだった。申し分のない実績と、ある程度は約束されたポジション。それでも五十嵐は、安定よりも挑戦へと舵を切った。しかし、FA選手として請われ、期待されて渡米したにも関わらず、五十嵐は早々に意識変革を迫られる。
「野球の違いというよりも、国の違いや文化の違いをすごく感じましたね。アメリカは、キャンプが始まるといったら、まずはキャンプ中に生活する家も自分で探さなければならない。そしてキャンプ地にも各自で行く。自分でどんどん考えて行動していかないと取り残されてしまうという状況でした。『これは日本の感覚のままでやっていたら、ついていけないし、置いていかれてしまう』と感じて、日本にいるときの考え方であったり行動であったりを考え直しましたね。日本は、一年間が保障される契約が前提だし、若い選手だったら寮に入って、住むところも食べるものも何にも困らず、食・住が保障されていますから」
苦しんだ3年間、そして選手寿命を延ばした変化球の習得
憧れのメジャーリーグでは、苦しんだ。初年度の2010年、メジャー1球団目のニューヨーク・メッツでの成績は、34試合に登板して1勝1敗2H、防御率は7.12。セットアッパーを任された矢先の故障者リスト(DL)入り、好不調の波の激しい投球……。自慢のストレートと数少ない変化球だけでは勝負にならない。新たな武器を習得する必要性を感じるのは必然だった。
そこからは、元来不器用とも思われた五十嵐が、剛速球に加えて変化球のコマンド豊富な投手に生まれ変わっていく。メジャー2年目の2011年終盤にはカットボールを、11年オフのドミニカ共和国でのウィンターリーグではスライダーを、そして12年にヤンキースのマイナーで「習得したことで3~4年は選手寿命が延びた」というナックルカーブをマスター。ドミニカ・ウィンターリーグでのスライダー習得は、カットボールをマスターしようと参戦した結果、想定外に手応えを得た“棚ボタ”でもあった。もがいた末に、“新たな挑戦”への考え方にも変化が芽生えた末の大収穫の数々。
「アメリカでトライすることへの恐怖心というのが取り除かれたような気がします。新たな一歩を踏み出すのはなかなか勇気がいるんですよ。トライの裏には常にリスクがあるから。トライするよりも“なんとなく”現状維持でやっていけたほうがラクだし、それでできるなら絶対にそっちのほうがいいって思っちゃうんですよ、人間って。でもその先を見据えてやろうと思ったら、そのときの自分だけでは絶対に物足りないんです。
例えば、日本の場合は12球団しかないじゃないですか。だから、対戦するバッターも(ピッチャーに)進歩や変化がないことに慣れてくるんですよね。いかに早く変化を自分にもたらして、相手の先をいけるかっていうときに、どんどん考えて実行していかないと、気づいたときにはもう結果が残せなくなっているというパターンは多いと思いますね」
現状維持からの脱皮を常に求めるのは、安泰な立場からメジャーを志した五十嵐にとっては、呼吸をするように当然のことだ。プロ野球選手として過ごしてきた10年以上のキャリアへの自信は失わぬまま、目を背けずに現実と対峙した五十嵐は、ある気づきを得る。
チャレンジに対する捉え方、根本的な考え方の変化
「行って気づいたことは、自分がすごく窮屈な考え方をしていたな、と。もちろん人って、経験の範囲内でその人にとっての“当たり前”ができていくと思うんです。自分が(誰かに)言われてきたこと、やってきたこと、置かれてきた環境が“すべて”と思ってしまう。
ただ、正しいと思っていたり、間違っていると思っていたことも、意外とそうじゃなかったという発見が多くありました。自分がトライしてダメだったことに対しても、合わないとか、自分ではできないとかっていうネガティブな発想になって止めていたことも、アメリカに行ったことによって、意外とこういう投げ方やこういう打ち方でも結果が残せるんだって気づいたんですよね。アメリカには、球が速いピッチャーや球を遠くに飛ばせるバッターが多いイメージがあったけど、意外とそうでもなかった。日本人のようなプレイヤーもたくさんいましたし、球が速くなくても抑えられるピッチャーも何人も見てきました。そういった中でどう自分を受け入れて、どう変化していくかっていうことを考えたときに、向こうに行ってからのほうが、すごく幅が広がったんです。
日本時代にできなかったことも結構できるようになったし、これまで当たり前に思っていたこととか、自分がコーチや周りに言われたことによる思い込みっていうのが、意外と全部取っ払えて、幅広い視野を持てるようになった気がしますね」
新たな挑戦をすることへの恐怖心が取り除かれ、これまでの常識や思い込みを捨てた五十嵐は、前述の通り、スポンジのように新球種を習得。そして、アメリカでの数多の予想外の出来事にも「僕、やったことがないことに対してすごく興味を持っちゃうんです」と前向きに取り組んでいく。今だからこそ笑って振り返ることができる異国の地でのエピソードが二つある。一つ目は後世の武器になるナックルカーブをマスターするまで、もう一つは(これは日本復帰後だが)ウィンターリーグでのエピソードだ。
「2012年の途中にブルージェイズからヤンキースに移籍することになって、マイナーにいたときにコーチから半ば強引にナックルカーブを覚えることを課せられたんです。初めは違和感もすごくて全然投げられなくて、『ふざけんな』と(笑)。でもフォークも落ちなくなっていたし、安定して使える強力な変化球が欲しかった。やるしかなかったんです」
ウィンターリーグの活用法
反骨精神と、指導者や年上の選手が放っておけない茶目っ気が覗く微笑ましい一コマ。本来であれば苦しいはずのことや大変なことも、この男は“新しい刺激”として面白がること、楽しむことを忘れない。ソフトバンク時代の2016年オフに参戦したメキシコのウィンターリーグでは、奇天烈な出来事に遭遇する。
「僕、メキシコ(のウィンターリーグ)で先発をやってるんですよ。先発をすることになった本当の経緯はわからないですよ? “ウィンターリーグへの参加が決まりました、代理人が五十嵐は日本のプロ野球で中継ぎとしてこれだけの成績を残したので、中継ぎで使ってください”と球団に伝えてるはずなんです、絶対に。
でも向こうに行って『君は先発として獲った』と言われたときに、どう普通の人は反応するかな?ってまずは考えるんです。『いや、そんなわけないだろ!リリーフしかできないよ』って言うのが、おそらく普通のリアクションじゃないですか。僕も先発と言われたときに『そんなわけはない』と、当然最初は言ったんですよ。でも、『やれって言われたらやるよ』って最終的に折れたというか、言っちゃったんですよね(笑)。どうなるかはわからないけど、やれることはやる、と。
ウィンターリーグに参加したそもそもの理由として、変化球を覚えたかったし、フォームの修正もしたかったので、投げる量が多ければ多いほどいいんですよ。だから、ポジティブな方向に発想を変えてしまった。向こうは先発を中4日で回すから、球数を投げられるしイニングもこなせるわけで、目的も満たせるし体力的にも鍛えられて面白いなと思い始めちゃって。最初は3イニングくらいから投げ始めて、2~3イニングと伸ばしていくんですけど、やっていくうちに意外とできんじゃんと思えてきたんです。それで、先発の調整の仕方もわかんないから、ストリングスコーチにも相談して、なるほどね、みたいな。それは非常に面白い体験でしたね」
武者修行のイメージのあるシーズンオフのウィンターリーグについても「何か目的があるから行く」とサラリと言ってのける。そして2011年にドミニカのウィンターリーグに参加した際のことも「決まるまでの2~3週間は公園で走ったり、キャッチボールをやったりしてね(笑)」と野球少年のように目を輝かせて懐かしむ。そう、野球が好きで好きでたまらなく、もっともっと“上”を常に追い求めた者にとっては、環境の善悪など二の次なのだ。
競争環境と練習環境について
「練習ってね、意外と場所はどこでもできるんですよ。いかに自分に何が足りなくて、何が欲しいかを知っているか。自分で考えて、用意された環境の中でどうするかを考えることがプロにとってはすごく重要なことだし、面白いところ。環境のせいには絶対にできない」
最近のプロ野球界では、育成契約を含めた抱える選手数の多寡、三軍制などの組織体制、それに付随する設備にも、チーム間で歴然とした差がついており議論の的になっている。五十嵐は、アメリカでは3球団に加えてメジャーリーグ、マイナーリーグの両方を体感し、日本ではヤクルトとソフトバンクと設備面、組織面がともに“両極”とも言われる球団に身を置いた。「良いに越したことはないけど、(環境が)揃ってないからできないって、絶対にそんなことはないんですよ」と環境差は不問に付したものの、強い口調でチームが強くなるためには競争が不可欠であることを説いた。
「自分の代わりがいるかどうかは大きいですよ。その環境が競争心を煽る要因になりますよね。人数が少ない状況でね、競争をしろって言われても、なんとなく周りが見えてるんですよ。ちょっとしたことで自分の立場が危うくなる選手が多ければ多いほど、競争が激しくなってくるわけで。自分と似たような選手、競争する相手が少なければ、『じゃあ、あいつに勝てばいいんだ。あいつに勝てば安泰なんだ』ってなっちゃうから、環境としては人数が揃っているほうが競争力は生まれやすいかなと思いますね。
僕のアメリカ時代の話をすると、3Aとかルーキーリーグにもすげぇ球を投げるやつがいたんですよ。そういう選手でもメジャーに上がれないんだって不安になったりもしたんですけど、そういう不安な要素があるから、じゃあどうしたら残れるか、やっていけるんだろうと考えることにつながりましたから」
球速→変化球→フォーム。剛球投手から考える投手へ
ホップ、ステップ、ジャンプ。紆余曲折がありながらも、傍目から見れば順調に飛躍し続けていた日本から海を渡ってはじめて、立ち止まること、自らをじっくり顧みることを余儀なくされたメジャー時代の五十嵐。そしてマイナーリーグ暮らしが大半となったメジャー2、3年目を経て2012年オフに日本球界に復帰した後は、荒ぶる投球フォームから配球のほとんどをストレートで押していた“イケイケドンドンな投手”から、“考える投手”へと変貌を遂げていた。創意工夫に富み、相手の打者を考えさせ、悩ませる投手になった。2014、2015、2017年の3度、セットアッパーとしてチームを日本一に導く獅子奮迅の活躍。ソフトバンク時代に行っていた象徴的な工夫に、投球練習の最後の一球にあえて山なりのボールを投げ、相手に満足にタイミングをとらせない、といったものがあった。
「ある試合で、投球練習の最後の一球を投げようとしたときにバッターのほうを見たら、タイミングをはかってるんですよ。そのとき、何かイヤな感じがしたんです。自分がイヤだなと思ったら、すぐに気づいて実行したり対処したりするべきだと思っていて。イヤな感じがしても、まぁ些細なことだから気にしないじゃなくて、もし仮に自分がダメだったときに、『あのときイヤな予感がしたんだよな~』と後悔するのもイヤじゃないですか。そのときそのときの自分なりの気づきを見逃さずにベストを尽くした結果、生まれた工夫が山なりのボールですね。おかしいなと気づいたことをクリアにしていく、自分が違和感にどう対応していくのかというのが非常に大事で」
“肩ができあがるのが早い”というリリーバーにとっての長所も「どんどん無駄を省いて、いかに肩を早く作るかっていうことを追求してきた結果」だ。また、最晩年は、球速へのこだわりはそのままに、変化球に加えてフォームでも相手を幻惑する場面が目立つようになった。1球ごとに足を大きく上げる、クイックモーションにする、さらに速いクイックで投げる、といった風に。こういった頭を使った投球が剛球のイメージ以上に定着したようにさえ思える。相手が抱くイメージを凌駕する投球スタイルから、常に進化することで相手が抱くイメージの先を行く投球スタイルへ――。プロ入り時の入団会見で語った「セールスポイントはストレートです。もっと考えたピッチングを身につけてやっていきたいです」という目標は、メジャーリーグでの経験によって結実したといっていいだろう。
五十嵐に、このような質問もぶつけてみた。もう一度プロ野球選手をやり直すとしても、先発よりもリリーフとして投げたいと思いますか――。
「いや、そりゃあ先発をやりたいっすよ(笑)。やっぱりピッチャーである以上、キレイなマウンドに上がって、最後まで立っていたいですよ」
リリーフ一筋で日米通算906登板を果たし、リリーバーの地位を上げた一人である、鉄腕にして剛腕の五十嵐亮太。栄華を誇っても、それを再び味わいたいとは思わない。とことん、新たな挑戦が好きな男なのだ。
 【参考】プロ野球 歴代登板数(NPB&MLB通算) トップ10
【参考】プロ野球 歴代登板数(NPB&MLB通算) トップ10