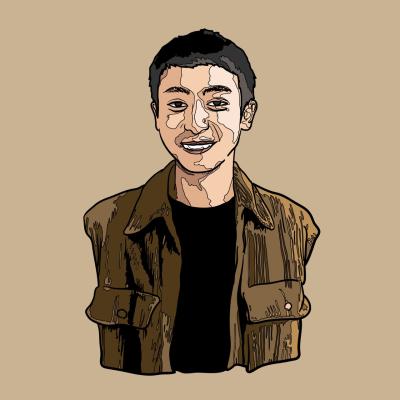球場観戦が叶っても、マスク着用、声出し・鳴り物は厳禁。手拍子・拍手での応援となり、たとえば東京ヤクルトスワローズの応援=神宮での“エア東京音頭”もいまや新しい応援様式になっている。
次に選手。大声を発するパフォーマンスは憚られ、手の平と手の平を合わせるハイタッチは自粛。歓喜の渦にあっても、大げさに喜ぶわけにもいかず、肘タッチやお尻タッチで控えめに喜びを分かち合う。(球場での鳴り物の応援がない分、フライボールを巡っての選手間の声掛け。守備位置、ベンチからの選手の声が球場でもテレビでもよく聞こえて、それはそれで楽しい)。
■話題の「上田新喜劇」
ベンチからの声はよく出ている(聞こえる)とは言っても、選手のダイナミックなパフォーマンスがあまり見られないのは寂しい。そこで台頭しているのが、ヤクルトの上田剛史を座長とする「上田新喜劇」を端緒とする“ノンバーバル(非言語)・パフォーマンス”であり“サイレント・パフォーマンス”だ。
上田は、2015年のスワローズが優勝したシーズンでは1番バッターを務め、シュアなバッティングと守備走塁のスペシャリストとして存在感がある選手だ。9月16日のDeNAベイスターズ戦で、最下位に沈むチームを鼓舞するようなフェンス激突のファインプレーで勝利に貢献し、残念ながら登録抹消となるも、チームのムードメーカーとしても欠かせない。
上田が今シーズン、ホームランを打った打者を迎える際、ベンチ横のカメラに向かって、ガッツポーズしたり拍手をしたりうなずいたり、もしくは何もせずにただただジッと見つめるパフォーマンス。カメラに声を発して何かを伝えるでもなく、「真顔」や「驚きの表情」などの主に“顔芸”で、カメラの向こうのファンに無言の語り掛けをする。大仰なボディランゲージや声で意思疎通をはかるのではない、ファンとのノンバーバルコミュニケーション。その上田の様子が、Twitterを中心にファンの間でまとめられて話題になり、当の上田も自身のインスタグラムに投稿してさらに拡散した。
その後、上田が「僕が教えました」とインスタで語っていた通り、リーグの垣根を越えて日本ハムにまで波及。矢野謙次一軍外野守備コーチ兼打撃コーチ補佐がインフルエンサーとなり、杉谷拳士、淺間大基、谷口雄也らが追随。日本ハムはチーム全体で日替わりキャストでは?というほど「日ハム新喜劇」化し、そのほか、福岡ソフトバンクホークス、オリックスバファローズもこの静かなる喜劇の上演を開始している。
球界の新喜劇の本家・上田は負けじと、高津監督のかつてのお家芸であるクリスタルキングのボーカル・田中昌之のカツラで登場するなど(上田は登場曲も「大都会」に)、80年代後半から90年代前半にプロ野球選手が意気盛んに芸を競い合った「オールスタープロ野球12球団対抗歌合戦」のような様相も呈してきている。
■主役だけでなく脇役も
これまでのホームランパフォーマンスは、ド派手なパフォーマンスか、お笑い芸人の一芸をパロディしたものが多かった。また、“演じる”当事者は打った選手本人=つまりは主役であった。
古くは西武ライオンズ黄金期の秋山幸二のホームイン時のバック宙。平成以降も、現・横浜DeNAベイスターズの監督、アレックス・ラミレスがヤクルト、巨人での現役時代に披露していた「アイ~ン!」「ゲッツ!」「ラミちゃん、ペッ!」。最近では、福岡ソフトバンクホークスの松田宣浩の「熱男~!」や西武・山川穂高の「どすこ~い!」、千葉ロッテマリーンズ・井上晴哉の“手刀パフォーマンス”。
いずれも、ホームランパフォーマンスはアーチストの専売特許であり、唯一演じることが許されたキャストであった。「一流の脇役になれ」という、故・野村克也の言葉に上田が従ったわけではないだろうが、脇役が主役を食う勢いで、ファンを楽しませ球界を席巻しているのが、今季のホームランパフォーマンスなのである。
「サイレント・トリートメント」。2018年4月。大リーグ1号を放ったロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平が、ベンチに戻って祝福されると思いきや、チームメートから無視されたことで話題になった、大リーグの儀式であり風習がある。
同じサイレントでもやや色は異なるが、どちらも観ていてファンを楽しませてくれる、サイレント・パフォーマンス。
今年、10月をもって活動を休止するアイドルグループ・欅坂46のデビュー曲にして代表曲の一つである「サイレントマジョリティー」の歌詞に、次のような一節がある。
“君は君らしくやりたいことをやるだけさ。
One Of Themに成り下がるな“
プロ野球は主役も脇役も揃い踏みしてこそ、最高のスポーツにしてエンターテイメントたりえてきた歴史がある。
上田剛史がたった一人で始めた「サイレントマイノリティー」であったパフォーマンスが、日本ハムをはじめ他球団に波及し、「サイレントマジョリティー」な一大ムーヴメントになりつつある。このコロナ禍の副産物が今後、どんな喜劇へと進化していくか、そしてどれだけ“劇団員”が増えていくか。2020年の異例ずくめのシーズンは、そういった面でも最後まで目が離せない。
=敬称略=