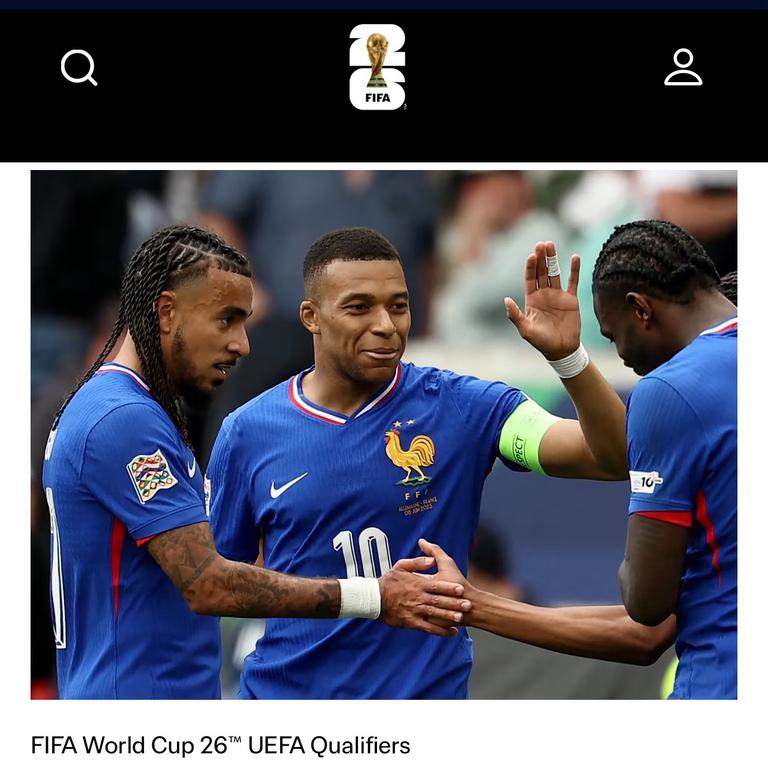クラブW杯を振り返ってみると、分かりやすい。戦力面で上回っていた欧州勢が上位を占めたものの、ブラジルのクラブの充実ぶりが目を引いた。これは、シーズンと大会の時期の関係によるところが少なくない。欧州は一般的に8月に開幕して翌年5月にクライマックスを迎える。一方、南半球にあるブラジルではシーズンの真っただ中にクラブW杯を迎えた。パルメイラス、ボタフォゴ、フルミネンセ、フラメンゴといった同国の出場4クラブが全て1次リーグを突破(4チームのトータルの1次リーグの勝敗は6勝5分け1敗)するなど予想を上回る好成績を残せたのは偶然ではないだろう。その中でもフルミネンセがベスト4に勝ち残って存在感を示したことは、改編された新規のクラブW杯の大会意義を高めたといえる。
ちなみに、12チームが出場した欧州勢は3チームが1次リーグで敗退した。1次リーグのトータルの戦績は22勝7分け7敗。各リーグが閉幕してからクラブW杯まで約1カ月近くの期間があいたこことで、チームのコンディションも整っていたとは言いがたかった(欧州時間に合わせ、試合キックオフが米国の昼に多く設定されたことも、ピッチ上のテンションが上がりきらなかった要因と考えられる)。2024/2025年シーズンの欧州チャンピオンズリーグ(CL)を制したパリ・サンジェルマン(フランス)は「2冠」こそならなかったが、メッシのいるインテル・マイアミ(米国)やバイエルン・ミュンヘン(ドイツ)、レアル・マドリード(スペイン)を倒して決勝まで勝ち上がり、大会を通じて勝負強さを示した。一方で、プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティー(イングランド)は1次リーグで3連勝と順当に決勝トーナメントに進んだものの、1回戦でアルヒラル(サウジアラビア)に3―4と足をすくわれた。欧州五大リーグで最も過酷なプレミアリーグでの消耗は激しく、リーグ5連覇を逃した状態の悪さを引きずったままの印象をぬぐえなかった。
さて、来年のワールドカップはどうだろうか。前回のW杯は中東のカタールが舞台だったことから、酷暑を避けるために11~12月という変則的な日程だった。来年のW杯は通常通り、6~7月の開催となる。つまり、クラブW杯と同じタイミングに戻るわけだ。2018年ロシア大会までと同じようなカレンダーで行われるため、欧州でプレーする選手にとっては、シーズンを戦い抜いたダメージをいかに回復させるかが重要になる。
実は同じシーズンに欧州チャンピオンズリーグ(CL)とワールドカップ(W杯)のタイトルをどちらも獲得した選手は多くない。どちらの大会でも決勝でプレーして優勝した選手に限ると、過去に9人のみ。そのうち6人は1974年大会のベッケンバウアーやミュラー(バイエルン・ミュンヘン×西ドイツ)で、その後は1998年大会のカランブー(Rバドリード×フランス)、2002年大会のロベルトカルロス(Rマドリード×ブラジル)、2018年大会のバラン(Rマドリード×フランス)の3人しかいない。例えば、2018年大会もフランス―クロアチアの決勝でプレーしたレアル・マドリードの選手はバランのほか、クロアチアのモドリッチしかいない(コバチッチは両大会ともベンチ入りしたが、プレーはしなかった)。成功し続けることがいかに険しい道かは歴史が示している。
 クラブチームとの両立を実現したモドリッチは、移籍後もチームを頂点まで導けるか(画像:FIFA.comより)
クラブチームとの両立を実現したモドリッチは、移籍後もチームを頂点まで導けるか(画像:FIFA.comより) 森保一監督が率いる日本は、来年のワールドカップ(W杯)で「優勝」を目標に掲げている。日本は過去に4度のベスト16が最高成績。簡単ではない目標だが、欧州のビッグクラブでプレーする選手が増え、前回W杯カタール大会ではドイツやスペインといった優勝経験を持つ国を倒した。新シーズンで欧州チャンピオンズリーグに出場するのは板倉滉(アヤックス)伊藤洋輝(バイエルン・ミュンヘン)堂安律(アイントラハト・フランクフルト)遠藤航(リバプール)南野拓実(モナコ)らがいる。
日本がワールドカップ(W杯)でベスト16に進んだ年の欧州CLの戦績を振り返ってみると、2022年に南野がリバプールで準優勝したが、出場は1次リーグでの4試合に限られた。2018年大会はドルトムント(ドイツ)時代の香川、2010年はウォルフスブルク(ドイツ)で長谷部誠が欧州CLに出場して1次リーグ敗退に終わっている。2002年に小野伸二がフェイエノールトで主力として欧州連盟(UEFA)杯(現欧州リーグ=欧州CLに次ぐ格付けの大会)優勝と、W杯ベスト16を達成したのが日本選手の最も成功した例と言えるかもしれない。欧州CLの決勝トーナメントで活躍し、なおかつW杯でベスト8以上の成績を残すことになれば、日本選手の歴史にとっては新たなステージを開拓したとことになるだろう。
欧州CLは8月19/20日、26/27日のプレーオフを経て、1次リーグは9月16日に幕を開ける。