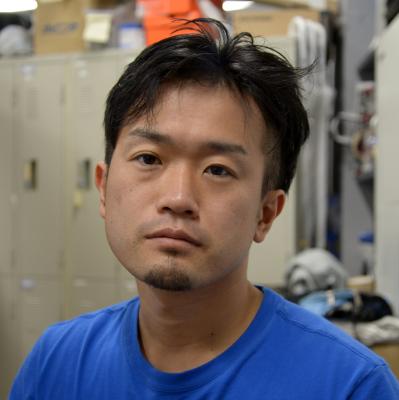ファイターは入れ墨だらけ。でもこれは神聖な奉納行事?
格闘技ファンにとってミャンマーの国技であり、神聖な奉納行事である格闘技であるラウェイは、昔から知る人ぞ知る存在だった。だが、多くの人にとっては「ムエ・カチューア」や「ビルマ拳法」などの呼称であり、「グローブを使わないキックボクシング」くらいの印象だったのではないだろうか。
「地上で最も過激な格闘技」と呼ばれるラウェイは、ムエタイのような肘打ちはもちろん、頭突きやせき髄攻撃、投げや首絞めなど、他の格闘技で禁じ手になるような技も認められる。試合終了を告げるラストゴングが鳴ったら「時間切れ」扱いとなり、判定での決着はつけない限りなく非現代的な競技だ。タイとの国境で行われている「草試合」を除けば、史上初めて公式国際大会が行われたのは2004年のこと。場所はミャンマーの商都ヤンゴンで、対日本人で行われた。その際に、唯一ミャンマー人を破った田村彰敏(格闘結社田中塾)は「頭突きは覚悟できていたが、脊髄攻撃があそこまで強烈だとは思わなかった。試合後も当分背中から痛みが引かなかった」と振り返っている。
日本でもたびたび試合が行われるようになった現在も、会場をざわつかせるルールは多い。何よりも初観戦者を驚かせるのが「タイム」のルールだろう。10カウントで立ち上がれそうにないファイターに対して、セコンドから「タイム」が入ると、1試合に1回ずつ、ファイターを救出して2分間休憩させることができる。目の肥えた格闘技ファンほど「負けたはずのファイターが、生き返る光景」に目を疑いたくなるのだ。こうしたルールには「発展途上国における発展途上競技でしかない」と危険視する声も少なくない。だが、日本でのラウェイ普及を目指す中村プロデューサーは、競技を未来にも残すために、現地の関係者とメディカルチェックなど、様々な方法を提案してきた。
「試合中に傷をチェックするのは日本の医師ですが、試合続行の判断はミャンマーから呼んだ医師が行っています。日本には病院へ直行できる体勢がすでにありますが、ミャンマーでも、この1年で何度も改善を提案し、血液検査の徹底や会場には交通渋滞を想定して救急車を呼ぶようにしました」(中村氏)
こうした「過激さ」への配慮をする一方で、ラウンドガールがリングに入らない、リング内で全員が裸足になるなど、奉納行事の根底を守っている印象もある。「地上で最も過激な格闘技」の売り文句はキャッチーだが、将来的に卒業して「世界一崇高な戦い」という本質に迫りたいとも中村氏は言う。
「ラウェイは正真正銘、神様に捧げる戦いです。地方興行を観ているお客さんにはとにかくお坊さんが多いんですよ。主催者側も大会前日は朝5時に起きて、会場周辺の仏塔を安全と成功を祈って廻ります。葉っぱをつけて、雨が降りそうだったらミャンマー式のてるてる坊主を作って、客入りが悪そうだと思ったら、開始30分前の入り口に水を撒く。全部プロモーターライセンスを取る前に徹底的に習わされました。できないなら認めないと」(中村氏)
ミャンマーのラウェイ関係者は、中村氏に何を求めていたのか。
ラウェイは日本人に「昭和」を回顧させる
 ©Getty Images
©Getty Images――ラウェイの際に行う仏教的な儀式は、すべて習ったんですか?
中村 ええ。心構えができていたので、朝5時に約束の場所で待ちました。ところが向こうは7時半に来て「昨日ちょっと飲み過ぎた」とか(笑)。いい加減だなと思いましたけど、すべて学んで「これらは日本でもやりますから」と約束したんです。ただし、会場でロウソクに火をつけることだけは、防災上できません。ラウェイでは試合前にバナナやココナッツなどの果物を入れたカゴを3つ捧げて、最後にココナッツの上にロウソクを立てるんです。しかし、後楽園ホールで火は禁止なので、立てられません。そう言ったら、向こうは「分かった」と。
――終わった後はどうするんですか。
中村 バナナは食べて、ココナッツは使い回しちゃいけないのでお焚き上げです。ココナッツは緑色でツタがついてないとダメなんです。毎大会ちゃんと検疫を通して、興行のためにミャンマーから持って来ています。
――日本人に、もっと味わってもらいたい競技の魅力は何ですか。
中村 「古くて新しい」と言うんですかね。昭和のプロレスにあった“匂い”が21世紀の今にプンプンする。これってプロレスと同じようにプロセスを一段ずつ作っていけば、コンテンツとして面白いと思ったんです。ファイターたちの誰かがヒーローになって、誰かがオオカミになる。今まで国際的に活躍して、国民的英雄になるミャンマー人がいなかったからこそ、生まれる可能性があると思った。あとは神聖さです。手を合わせて先祖を崇拝するとかの思想や宗教観。これらは僕らが幼稚園の時に習ってきたものに近いので、刺激を求める若者だけではなく、僕らのお父さん世代が懐かしめるものも意識しています。
――中村プロデューサーは新日本プロレスの社員からZERO-ONE社長にいたるまで、長く、プロレス関係者でしたが、そもそもどんな経緯でラウェイに携わるようになったのですか?
中村 今から2年前、プロレス興行をミャンマーでやったのがきっかけです。2000人くらいの集客は期待できたけど、当時は軍事政権下で、物事が進まない国だったので、やれるかやれないかがグレーでした。結局、土曜日にやらせてもらうはずが、10日前になって「政府の会合が入ったから体育館を使えない」と言ってきたんです。その時、ラウェイ連盟が「前日の金曜日なら我々の専用スタジアムを貸せるぞ」と助け船を出してくれました。ただし、絶対儲からないからやめる選択肢はないのかと。
――絶対にペイできないということですか?
中村 できません。でも、選手も全員呼んでいましたし、ドキュメンタリーとして、テレビのキー局が僕を追ってくれていました。成功しても失敗しても、放送はあります。それなら前のめりに倒れるか、引いて倒れるかだけの問題だったので前者を選びました。その結果、個人で1千万円単位の損失を被りました。
――失敗のリスクを背負っても行ったモチベーションはどこから来たのでしょうか?
中村 アントニオ猪木さんやその周辺のパワーを見てきたので、その影響でしょうね。猪木さんは誰もしたことのないことを狙う人で、ロマンがありました。だから最初にミャンマーでプロレスをやった人になれたら、そこにお金が付いて来なくても行こうと思ったんです。
――いわゆる「昭和」の豪快さでしょうか。
中村 よく言われたイケイケドンドン、三歩進んで二歩下がるの成長期です。猪木さんに関してはモハメド・アリとの異種格闘技戦とか、僕は、当時の大風呂敷に心躍らされた世代です。新日本プロレス勤務で13年間、その姿を見ることができました。結局、ミャンマーのプロレス興行では、ビザや興行ライセンスをラウェイ連盟がすべて発行してくれました。記者会見の時にはタイやバングラデシュからも集まって400人くらい来てくれたと思います。
――日本では考えられない数ですね。
中村 ミャンマー史上初のプロレス興行というのもあったんですけど、だからこそある記者は「プロレスはやらせだろ?」と聞いてきたんです。僕が「プロレスはプロレスだ。じゃあラウェイは何なんだ? ラウェイもあくまでラウェイじゃないか」と。そこから話が転じて、今度はラウェイ興行を日本で行うことになります。ラウェイの魅力や強さをミャンマー国外に示すために、僕はできることはします。ただし10年くらい前に日本で、対抗戦をやろうとしたときは、当時の国際情勢もあって、ファイターが日本に入国できず、中止になっています。これは、僕たちではどうにもなりません。プロモーターのリスクとして、入国できない選手をブッキングして試合をすることはできません。その後、ミャンマーの人が入国できる状況になり、おととしの7月にトゥントゥンミンを『巌流島』に出すことになりました。
――当時のエース級ですが、在日コンゴ人のルクク・ダリに一本負けしました。
中村 ミャンマー陣営は強さを証明したくて最初から英雄を出してきたんです。観戦ツアーまで組む力の入れようだったのに、速攻で惨敗。そうするとミャンマー側からは、言い訳が出てきます。「今度はダリをミャンマーに呼んで、ラウェイで勝負させろ」とか「トゥントゥンミンが負けたのは、彼の実力じゃなくてルールのせいだ。ミャンマーまで説明に来い」とか。「行って済むなら行きますが、みっともなくないですか?」と反論しました。こうした意見のぶつかり合いの中で、いつしか『ミャンマーでいろんなことをやりたい』と思うようになったんです。ちょうどミャンマー投資の第1次ブームでしたしね。今は第2次ブームが来ています。
「NATO」と揶揄される日本人にはなりたくない
 ©善理俊哉
©善理俊哉――どういったことに苦労しますか。
中村 最初は信用してくれないことでしたね。日本人は“NATO”と呼ばれているからなと。
――もちろん大西洋条約機構の略称ではありませんよね?
中村 それで隠しているんですけど「No Action, Talk Only」の略です。日本はクオリティへの信頼は抜群なのに「話すだけして行動に移らない」という意味です。中国人はその場で買うものを全部買っちゃうし、韓国企業は決済できる人間が直接来て決めちゃう。ところが日本はリサーチャーが何人も来て、稟議を通して、また来る。長い期間をかけて、ある程度の保証がないと白紙になる。「俺は違うよ、やるならやるよ」と。彼らもそれができるかどうかから試しているのが分かりました。
――ミャンマーでのスポーツはどんな現状ですか。
中村 プロスポーツはサッカーとラウェイだけです。サッカーリーグは小規模ですけど進行されているので、少しずつレベルは上がっています。ミャンマーは人口や資源など、様々な要素から考えて、タイ以上の経済的潜在力があると言われています。ただ、基本的に潜在力を導く指導者がいないんです。ラウェイはコンテンツとして魅力がある。でも日本で流行らせるにもすぐは無理。土台作りは約3年かかると思いますが、海外メディアが拾ってくれるようにはなりました。
――新しい競合組織みたいなのは出てきていますか。
中村 ミャンマー国内のプロモーターは元気がなくなってきましたね。日本大会のせいじゃないとはいえ、日本大会ってほぼ国際試合ですよね。観やすいわけですよ。あと、向こうでSNSとかいろいろな形式で無料ライブ配信が始まったので、お客さんが来なくなってしまいました。「SNSなんて俺たちには関係ない」と言っていましたが、実際にプロモーターの試合数は減ったんです。その中で僕はとにかく地上波でヒーローを作るということを、1年半言い続けてきたら、民放地上波の最大手が興味を持ってくれました。NATOかどうかを試された僕も、こうした契約を結べるようになったんです。
アジアの商談は何より回数。あとはスターを誕生させるのみ
――次に目指すのは何ですか。
中村 ミャンマー人の国際的な活躍をまずミャンマー人に教えてあげたいです。例えば開催中の平昌オリンピック。ミャンマーに行ったら、冬季オリンピックをやっていることすら知りません。軍政の影響で射撃の名手はいるので、夏季オリンピックには毎年参加できていますが、冬季は過去に出場者ゼロです。異様に盛り上がるのはアジア競技大会の東南エリア版のSEAゲームですね。
――ラウェイ日本大会に2度出たブロニカもボクシング競技で出たことがある大会です。
中村 ということは、スポーツに興味がないわけではありません。単に活躍できる選手がいないだけなんです。そこを意識して、昨年9月の大会からは、現地で中継特番を毎大会放送してもらっています。
――最終的な理想にはどんなものを描いていますか。
中村 ミャンマーの国技を日本でブラッシュアップして返すのが一番です。崇拝であることを確認してもらう、プラス、世界に配信することです。
――そのための商談として、先に挙げた「昭和」の活力で、残そうと思っているものはありますか?
中村 AIや仮想通貨みたいなものが出てきてしまうと、若手に知識で太刀打ちできません。でも、ビジネスで最強なのは今でも対面回数だということを、我々のILFJ(国際ラウェイ連盟ジャパン)の代表にも教えられてきました。本当に何かしたいと思ったら、今後も小さな用事でも、足を運ぶつもりです。コネクションというのは、お金の前に顔なんです。「他人の家に上がれて、初めて一人前の営業マン」と言われて育ったんですけど、特に南アジア一帯は、対面回数で成功率が高まる感覚はありますね。
山中慎介、伝家の宝刀「神の左」 KO奪取の秘訣は「距離感と下半身」
昨年8月、山中慎介(35=帝拳)は高校時代を過ごした京都でルイス・ネリ(23=メキシコ)に4回TKO負けを喫し、5年9カ月の長期にわたって12度防衛してきたWBC世界バンタム級王座を失った。3月1日にはリベンジと返り咲きを狙って東京・両国国技館でネリとの再戦に臨む。互いに手の内を知っているサウスポーの強打者同士だけにKO決着は必至といえる。勝負そのものはゴングを待たなければならないが、どんな結果が出たとしても変わらないものがある。それは山中のV12という実績と左ストレートのインパクトの強さだ。戴冠試合とネリとの初戦を含めた14度の世界戦の戦績は13勝(9KO)1敗。世界中の猛者を相手にする大舞台で記した数字としては驚異的なものといっていいだろう。しかもKOに結びつけたダウンのほとんどが「神の左」によるものである点も興味深い。選手生命を賭したリベンジマッチを前に、山中の半生をあらためて振り返り、そしてKO量産の秘訣を分析してみよう。(文=原功)
中国のボクシング市場開拓に、日本はどう向き合うべきか?
今やボクシング界で、日本人世界王者は男子10人、女子4人。かつての常識では考えられぬ数まで増えたことで「王者の希少価値」を見直し、日本は一定の独自規制もかけ続けている。対象的に国際社会では新王座の乱立がとどまるところを知らず、現在は中国の本格的なボクシング市場開拓が、それに最も拍車をかけている。ボクシングで、日本は中国とどう向き合おうとしているのか。(文:善理俊哉)
時代とともに変わっていくボクシング界 大橋秀行×池田純対談後編井上尚弥、2018年はバンタム級へ 「緊張感のある試合を」井上尚弥は、なぜ圧倒的に強いのか? 大橋秀行会長に訊く(前編)