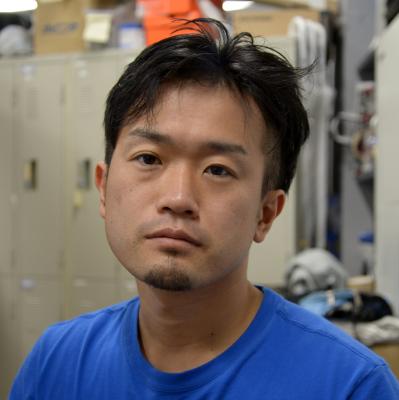中国で始まったローカル王座のプレセール
 ©善理俊哉
©善理俊哉昨年だけで、日本ボクシング界では男子10人、女子1人の新世界王者が誕生した。これは日本にとって史上最多。充実の秘訣には、約百年の文化で育成プログラムを培ってきたことや、経済的アドバンテージからマッチメークの主導権を握りやすいことなどが挙げられる。そして、チャンスが拡大したことも大きい。挑戦できる世界王座はWBA(世界ボクシング協会)とWBC(世界ボクシング評議会)のもののみから、IBF(国際ボクシング連盟)とWBO(世界ボクシング機構)のものも可能になった。この緩和ひとつでも長く論争した日本とは裏腹に、団体側は、スーパー王者、名誉王者、暫定王者といった「別の世界王者」を設け、スター選手の争奪戦に奔走している。これに古い関係者たちが「世界王座の価値がなくなる大廉売(セール)だ」と嘆くのは無理もなく、その背景には、世界王者になっても「車を買えない無名選手」が現れるようになり、女子の世界タイトルマッチには、なかなか黒字が見えない苦境がある。
日本ボクシング界を統括するJBC(日本ボクシング・コミッション)やJPBA(日本プロボクシング協会)は、王者やタイトルマッチの価値を守るために、暫定王座決定戦に最低限の規制をかけ、日本も対象となるローカル王座が新設されても、公認には慎重となり続けている。
団体側は、様々な王座を新設している。身近な例が「中国のためのローカル王座」だ。プロボクシング文化の乏しかった中国に、いち早く投資を始めたWBOには、アジア太平洋王座、東洋王座、中華圏王座、中華圏ユース王座などがある。これが軌道に乗ると、最近はWBA、WBC、IBFもアジア王座などを設けて参画し、それぞれが中国国内王座もつくった。狙いは団体同士の権力闘争とも承認料などの金銭収入ともいわれているが、JBCの安河内剛事務局長は「現時点ではこのテコ入れが、競技力向上に結びついていない」と見ている。
「試合会場に行ってみて、今度はそんな王座ができたのかと驚くことも多くなりました。王座を争わせることで試合をブランディングすることは大切ですが、競技レベルが上がっていません。日本の新人王トーナメントで上位に食い込める選手はまだ中国には少ないでしょう。それに、歴史が浅い分、防げるはずの運営トラブルも多いんです。昨年12月に陝西省で起こった死亡事故は、医療機関と連携していればまず救える命でした。たとえば各委員会を設けるような、日本で当たり前のノウハウを彼らは知らない」
長年、日本が重宝してきたローカル王座であるOPBF東洋太平洋にも、中国を意識した若年層向けのユース王座、さらにはシルバー王座が設けられた。
「アジア・ボクシングの主導権が日本から中国に渡る可能性はある。それで“持ちつ持たれつ”の関係になれるのなら、日本が中国の手本になって育てるような参入も悪くないと思いますが、中国が組織を固められなければ、身を委ねるリスクは大きくなります。日本には新人王トーナメントなどの育成プログラムがありますが、彼らにはこうした発想がない以前に、コミッションや協会のような統括組織がない。選手が続々と育つようなシステムを確立させなければ、ムーブメントの継続はあり得ないでしょう。でもそう気づいた時、もし経済が悪化していれば、もはや改革の意欲も湧かないまま衰退してしまいます」(安河内氏)
ローカル王座が増え続ける中で、JPBAは、昨年、WBOアジア太平洋王座のみを公認した。非公認の王座も、国内での防衛戦を行えないことを条件に、外国での挑戦を認めている。世界ランキングに入るチャンスをつぶさないためだ。一方で、日本ユース王座や日本女子王座といった新王座を2つ設けるなど、「王座の希少価値を高める」とは異なる方針をいよいよ取り始めている。同協会の渡辺均会長は「王者が多いことを前提に、競技をどうかPRできるかが現代の鍵だ」と話し、「好カードや好ファイトで中身が充実することが、“あの王座を獲りたい”と思うような威厳につながる」と付け加えた。また、中国ボクシング界がスポンサードに恵まれていることについては、一過性の可能性もあると冷静だ。
「カジノ資本やスター誕生で一大ムーブメントを起こしたマカオや香港は、このチャンスに土壌を固められず、あっさり下火になりました。中国本土も潤い続けると決め込むのは危険です。日本には日本の育んだ文化がある。たとえば出場選手たちが試合チケットを売るシステムには、“夢がない”、“プロスポーツ選手のあるべき姿ではない”と揶揄されながらも、人気低迷期に最低限の安定感を持たせたと思っています」(渡辺氏)
中国人選手の手本的日本人が現れる
 ©Getty Images
©Getty Imagesそんな“チケット手売り”の立場から、一躍、中国ドリームをつかんだ日本人第1号は、現WBO世界フライ級王者・木村翔(青木)だ。昨年7月、中国ボクシング界の国民的スターである鄒市明(中国)から大番狂わせで王座を奪取。現地上海の取材で発言した「アルバイトで生計を立てている」という日常は、中国人のイメージする「プロスポーツ選手」の先入観と異なり(おそらく日本の先入観とも異なるが)、そのシンデレラ・ストーリーを崇拝されている。所属先の有吉将之会長は、木村に関して、台湾、香港、中華系国民の多いシンガポールなど様々な地域からも商談が多いというが、決して浮足立った様子はない。
「実際に行かないと分からないことも多いんです。取材に来た記者から“木村さんは中国でヒーローですよ”と聞いても、現地でデパートやレストランに入っても誰にも気づかれない。結局こんなもんかと思っていたら、ボクシング界の反響はたしかにすごくて、“追っかけ”がいたりする。木村を日中のどちらを拠点にさせるべきか、様子見の段階です。日本にも需要は十分ありますから」
国家主席の「好きな競技」で一気に追い風に
中国プロボクシングの歴史は浅い。『Boxrec.com』に残る範囲で最も古い興行は2003年の雲南省・昆明で、当時は法規制の抜け道を縫うようにほそぼそと行われていた。2009年には東京のディファ有明で内藤大助(宮田)の持つWBC世界フライ級王座に熊朝忠(中国)が挑んだが、この試合は開催の3日前まで中国本土初の世界タイトルマッチ開催へ進んでいたことを記憶しているスポーツファンもいるかもしれない。2012年11月25日に同じ熊でようやく実現した世界タイトルマッチ開催も、「スポーツ」ではなく、あくまで「テレビ番組のいち企画」として押し通されたという。ところが、この一戦で中国は、政治の第一人者である習近平氏がボクシングを「好きなスポーツ・ベスト3」に入れていたことを確認し、本格始動への足がかりをつかむ。翌2013年から昨年にかけ、中国の年間試合数は1300パーセントまで膨らみ、昨年1月にマカオで行われた多田悦子(真正)と蔡宗菊(中国)のIBF世界ミニフライ級タイトルマッチは、後日、視聴者数が4億だったと発表された。日本の視聴率で考えれば315%の巨大な数だが、中国人たちは「旧正月、国営放送、中国史上初などの好条件がそろえば、まったく不思議な数字ではない」という。
まだ不安定だが、もう無視できない中国ボクシング界。そんな壮大なフロンティアに、日本は今後も「戦略的な互恵関係」を模索していくべきだ。しかし、正そうとしている秩序を完全に見失ってもいけない気もしてならない。
井上尚弥は、なぜ圧倒的に強いのか? 大橋秀行会長に訊く(前編)
さる5月21日、WBO世界スーパーフライ級2位のリカルド・ロドリゲス(アメリカ)にTKO勝ち。WBO世界スーパーフライ級王座の、5度目の防衛に成功した井上尚弥。その衝撃的な強さの秘密はどこにあるのか? 井上を育てた大橋ジム・大橋秀行会長に伺った。
井上尚弥、2018年はバンタム級へ 「緊張感のある試合を」
その強さは圧倒的だった。30日に7度目の防衛戦に臨んだ井上尚弥は、世界ランク6位のヨアン・ボワイヨを相手に第1ラウンドから力の差をまざまざと見せつける。そして3ラウンドのうちに3度のダウンを奪い、TKO勝利を収めた。試合後、スーパーフライ級への物足りなさを隠さなかったモンスターは、自身の野心を口にした。(文=VICTORY SPORTS編集部)
亀田興毅×大毅「和毅は、覚悟を決めたんやと思います」
ボクシング界に現れた熱血指導のオヤジと血気盛んな3兄弟。ブームを巻き起こし、一転してバッシングにさらされた「亀田家」は常に、世間の関心の対象だった。2015年に世界4階級制覇の長男・興毅、2階級制覇の次男・大毅が引退し、元WBO世界バンタム級王者の三男・和毅は昨年10月から協栄ジム所属となった。そして父・史朗は地元の大阪でアマチュアボクシングのジムで会長を務めている。家族が別々の道を歩む中、興毅と大毅が語る、「引退」「ボクシング」そして「家族」――。
飯田覚士。元世界スーパーフライ級王者が歩む、異色のセカンドキャリア
リング上でベルトを巻き、ガッツポーズを見せる。スポットライトを浴び、華々しい現役生活を過ごせるボクシング選手は一握り。だが、世界王者に輝いたボクサーも、引退後の生活はあまり知られていない。元WBA世界スーパーフライ級チャンピオンの飯田覚士氏が、現役引退後、何をしているのか。
時代とともに変わっていくボクシング界 大橋秀行×池田純対談メイウェザー330億円、敗れたマクレガーも110億円。世紀の決戦の意義とは